- 更新日:2025年7月31日
- 公開日:2025年7月31日
なぜ保育園は人材が集まらない?経営者が知るべき人手不足の根本原因と解決のヒント
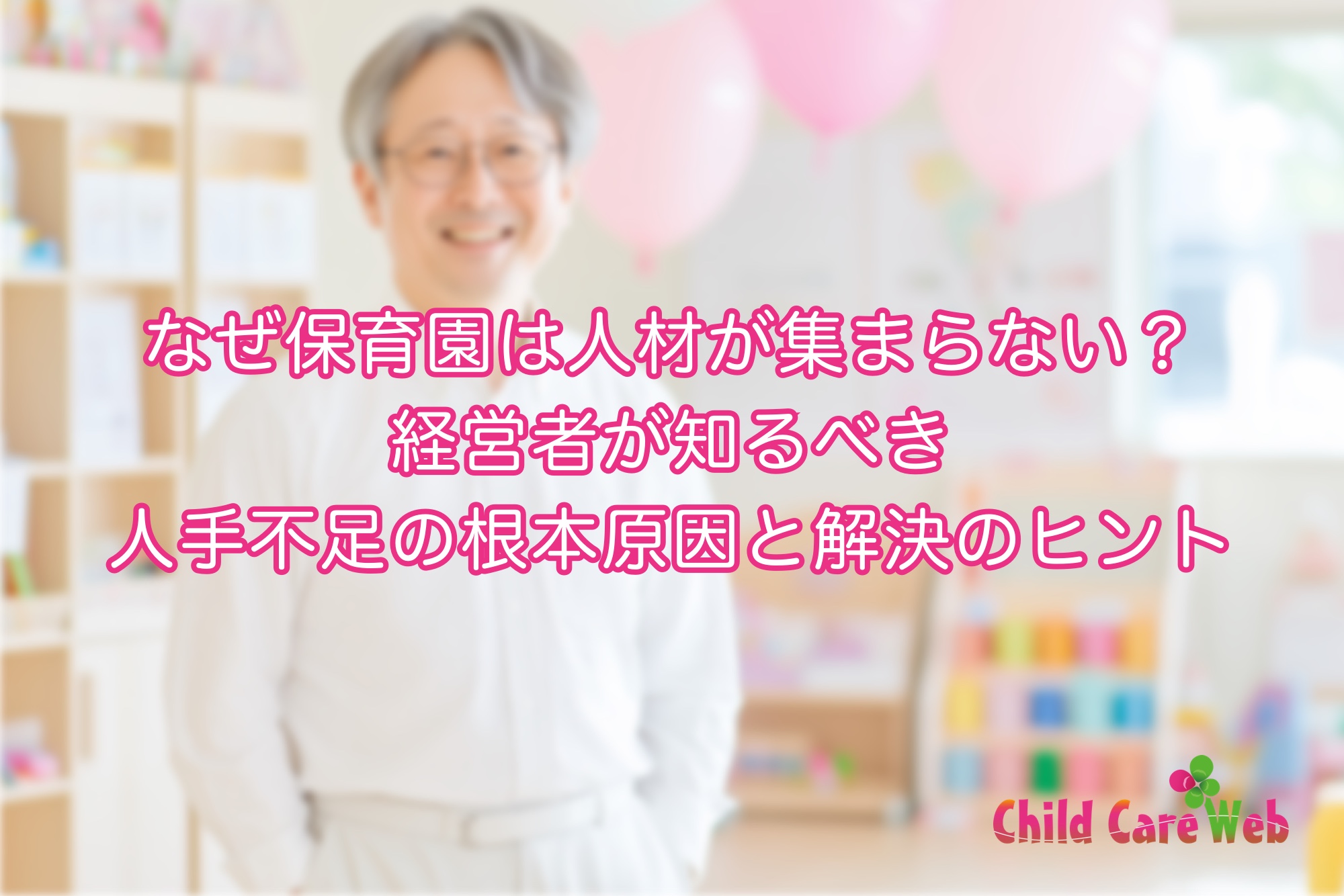
1. 保育士不足の構造的な背景とは
1-1. 保育士の供給数と離職率の現状
・資格取得者は増えても現場に定着しない理由
保育士の資格取得者は毎年一定数存在するものの、実際に保育現場で働く人数はそれほど増加していません。その理由として、職場環境や労働条件への不安が挙げられます。特に実習時点で過酷な業務を体験し、保育の現場を敬遠する傾向が見られます。
・新卒保育士の3年以内離職率の実態
保育士の離職率は高く、特に新卒で就職した若手保育士の多くが3年以内に現場を離れる傾向にあります。人間関係のトラブルや指導の不一致、労働時間の長さ、保護者対応などにストレスを感じやすく、継続勤務が難しい現実があります。
・「潜在保育士」数と復職のハードル
一度は保育士資格を取得しながらも現場に出ていない「潜在保育士」は全国で数十万人規模といわれています。しかし、ブランクや年齢、体力面への不安に加え、最新の保育制度やICT活用への不慣れも復職をためらわせる要因となっています。
・業界全体の人材流動性の高さ
保育業界では人材の流動性が非常に高く、年度途中での離職や転職も珍しくありません。その背景には、職場による業務量の差や待遇格差、保育方針の違いなどがあり、現場での不満が転職の引き金になることが多く見られます。
1-2. 賃金と労働環境が及ぼす影響
・一般職との給与格差と地域差
保育士の平均給与は全産業平均よりも大きく下回っており、特に若年層の給与水準においてその差が顕著です。また、都市部と地方で賃金差が大きく、同じ業務内容でも待遇の地域格差が人材確保をさらに難しくしています。
・長時間労働と持ち帰り仕事の実態
保育士の仕事は園内だけにとどまらず、自宅での書類作成や行事準備といった「持ち帰り業務」も多く発生します。表面的には定時で帰れるように見えても、実際には長時間労働が常態化しており、離職要因の一つとなっています。
・職員配置基準がもたらす人員不足
国の職員配置基準では、年齢ごとに必要な保育士数が定められていますが、現実にはギリギリの人員で運営されている園が多いのが実情です。突然の欠勤などに対応しきれず、保育の質を保てない状況が慢性化しています。
・心理的負担と燃え尽き症候群
子どもたちの命を預かるという重大な責任に加え、保護者対応や同僚との関係性など、保育士は多方面からのプレッシャーを受けています。過剰な期待に応えようとする中で、心身の疲労が限界を迎え、燃え尽きてしまうケースもあります。
1-3. 保育ニーズの変化と制度のズレ
・待機児童ゼロ政策と保育士確保のミスマッチ
政府は「待機児童ゼロ」を目標に保育施設の新設を推進してきましたが、保育士の確保が追いつかず、現場は常に人手不足の状態にあります。施設はあっても職員がいないため定員まで受け入れられず、政策と実態が乖離しています。
・都市部集中と地方の慢性的不足
都市部では保育士の奪い合いが起きる一方、地方では求人を出しても応募がほとんどない状況が続いています。居住環境や賃金水準の違いが要因となり、地域によって人材確保の難易度に大きな差が生じているのが実情です。
・多様な保育ニーズに対応しきれない体制
近年は延長保育、一時預かり、企業主導型保育など、保育ニーズが多様化しています。しかし、現場の人員やシステムが追いつかず、保育士一人あたりの業務が煩雑化。結果として職場満足度が低下し、人材が定着しにくくなっています。
・保育無償化の影響とその副作用
保育無償化により保護者の利用ニーズは高まりましたが、保育士の処遇や人材育成には直接つながっていないのが現状です。業務量が増加する中で人員は増えず、現場の負担が集中するという副作用が浮き彫りになっています。
2. 保育園経営に与える影響とリスク
2-1. 定員割れと経営悪化の連鎖
・人手不足による園児受け入れ制限
保育士が不足している状況では、園児の受け入れを希望されても定員通りに対応できず、やむを得ず入園を断るケースが発生します。収入源である園児数が減ると、経営全体に影響が及び、さらに職員の確保が難しくなる悪循環を招きます。
・欠員補充の人件費増と収支悪化
急な欠員や退職者が出た場合、短期的に人材を補うため派遣保育士や高額な人材紹介サービスを利用することがあります。これにより人件費が予算を大きく上回り、運営コストが圧迫されて、収支バランスが崩れてしまうリスクが高まります。
・保護者からの信頼低下による離脱
人手不足によって保育の質が低下したり、職員の入れ替わりが頻繁に起こったりすると、保護者の不安が募り、他園への転園や口コミでの評価低下に繋がります。一度信頼を失うと回復には時間がかかり、経営にも長期的な影響を与えます。
・求人広告・人材紹介に依存する経営構造
保育士の確保が困難な状況が続くと、常に求人広告や人材紹介会社に頼らざるを得なくなり、経営が広告依存型になりがちです。費用がかさむだけでなく、自園に合った人材を継続的に確保する仕組みを育てにくくなるという弊害もあります。
2-2. 職員への負担集中による質の低下
・残業・有給未消化が常態化する現場
人手が足りない状況では、限られた職員に業務が集中し、残業が常態化します。さらに、休暇を取りづらい雰囲気が蔓延し、有給休暇が消化されずに蓄積されることも。こうした状態は、働く環境の悪化とさらなる離職につながります。
・チームワークの崩壊とトラブルの増加
慢性的な人員不足の中で業務が回らないと、些細な行き違いがトラブルに発展しやすくなります。業務の押し付け合いや感情のすれ違いが蓄積し、職員間の信頼関係が崩れることで、チーム全体の機能不全を招くケースも少なくありません。
・離職ドミノによるさらなる人手不足
一人が辞めると業務の負担が他職員にかかり、その職員も疲弊して退職するという「離職の連鎖(ドミノ)」が起きやすくなります。こうした負の連鎖は園全体の運営体制を根本から揺るがし、再建には多大な時間と労力が必要となります。
・保育の質・安全性の低下リスク
職員が慢性的に不足している状況では、子ども一人ひとりに十分な配慮を行うことが難しくなり、事故やトラブルのリスクが高まります。結果として保育の質が下がり、園の信頼性や保護者の満足度にも悪影響を及ぼす可能性があります。
2-3. 園全体の運営効率と採用競争力の低下
・園長・主任が現場に入らざるを得ない実情
人員不足の中では、本来マネジメントや職員支援に注力すべき園長や主任クラスの職員が現場に入る必要が生じ、管理業務が後回しになります。これにより園全体の運営効率が落ち、経営判断や組織改善に手が回らなくなる傾向があります。
・研修・育成コストが継続的に発生
離職や入れ替わりが多い園では、新人職員の研修や教育に常に時間とコストが必要になります。職員が定着しないため、育成投資が園内に蓄積されず、常に一から指導を繰り返す非効率な運営体制になってしまうという課題があります。
・経験者の獲得競争と条件提示の限界
経験豊富な保育士は人気が高く、複数の園から引き合いがあります。そのため、好条件での待遇提示が求められますが、すべての園が予算的に対応できるわけではありません。結果として他園に人材を奪われる状況が続いてしまいます。
・評判サイト・口コミによる採用難の悪循環
保育士向けの口コミサイトやSNSで悪い評価が広がると、新たな求職者の応募が減少します。また、現場の雰囲気や働き方を重視する求職者にとって悪評は大きなマイナスとなり、採用活動がより困難になるという悪循環を引き起こします。
3. 経営者が取るべき持続可能な人材確保戦略
3-1. 働き続けたくなる園づくりの工夫
・業務分担の見直しとICT導入
人材不足が続く中で、限られた職員に業務が集中しないようにするためには、業務分担の最適化が重要です。加えて、登降園管理や保育日誌などのICT導入により業務を効率化することで、現場の負担軽減と時間外労働の削減が期待できます。
・人間関係改善と定着支援の取り組み
働きやすい職場環境をつくるには、人間関係の良好さが欠かせません。定期的な面談や第三者による相談窓口の設置、新人との関係づくりをサポートするメンター制度などを導入することで、職員の定着率向上につなげることが可能です。
・小規模でもできる福利厚生の工夫
大規模な予算を用意できなくても、誕生日休暇の導入や昼食補助、制服の貸与など、小さな工夫で職員の満足度を高めることができます。福利厚生の充実は、求人時の魅力にもなり、他園との差別化にもつながる施策の一つです。
・職員の声を反映する運営体制
現場の課題や改善点を経営側が的確に把握するには、職員の声を積極的に取り入れる運営体制が重要です。定例会議や匿名アンケート、意見箱などを設置し、現場の声を吸い上げて実際の改善につなげることで信頼関係を構築できます。
3-2. 採用力強化のための広報とブランディング
・採用ページやSNSで園の魅力を発信
採用活動においては、求人媒体だけに頼らず、自園のウェブサイトやSNSで保育方針や職員の雰囲気、園内の様子を発信することが効果的です。写真や動画を活用し、働きたくなる職場のイメージを視覚的に伝える工夫が求められます。
・実習生・ボランティア受け入れの強化
将来の採用候補となる学生や地域住民との接点を増やすため、実習やボランティアの受け入れを積極的に行うことが大切です。園の雰囲気を体感してもらい、実際の職場としての魅力を理解してもらうことで、自然な採用につながります。
・既存職員の紹介制度活用
現在勤務している保育士の紹介を通じて新たな人材を確保する「リファラル採用」は、ミスマッチの少ない採用方法として注目されています。紹介した職員への報奨制度を設けることで、紹介の動機付けにもつながります。
・他園との差別化ポイントを明確に
採用においては、「なぜこの園で働きたいと思ってもらえるか」を明確にすることが重要です。保育方針や職員育成制度、福利厚生、立地条件など、自園独自の強みを整理・発信し、他園との差別化を図る戦略が必要となります。
3-3. 国や自治体の支援制度の活用
・保育士確保事業・補助金の最新情報
国や自治体は、保育士不足への対策としてさまざまな補助金や事業支援を行っています。採用時の初期費用を補助する制度や就職支援交付金など、各種支援制度を正しく把握し、計画的に活用することで経営の安定化が図れます。
・復職支援研修・資格取得支援制度
潜在保育士の復職支援や無資格者の資格取得を支援するための制度も多く用意されています。これらを活用することで、職員育成にかかるコストを抑えつつ、新たな人材を中長期的に確保することが可能となります。
・市区町村ごとの家賃補助・加算制度
一部の自治体では、保育士の家賃補助や給与への加算制度を実施しています。特に都市部においては、生活コストを補うこうした支援が採用活動の強力な武器になります。最新の情報を確認し、効果的に制度を導入しましょう。
・中途採用・潜在保育士向け制度の紹介
中途採用や復職を希望する保育士に特化した就職フェアや支援制度が多数存在します。制度の活用方法を園内で周知し、ホームページなどでも積極的に紹介することで、幅広い求職者に自園の取り組みを知ってもらうことができます。


