保護者向けアンケートの作成方法
Child Care Webをご利用いただいている親御さまに向けて Microsoft Forms・Googleフォームを使ったアンケート実施する方法をご説明します。
どちらのフォームも、回答のしやすさや内容に違いはありません。すでにお持ちのアカウント(Microsoft または Google)のいずれかで、ご利用しやすい方から作成を行なってください。
Microsoft Forms
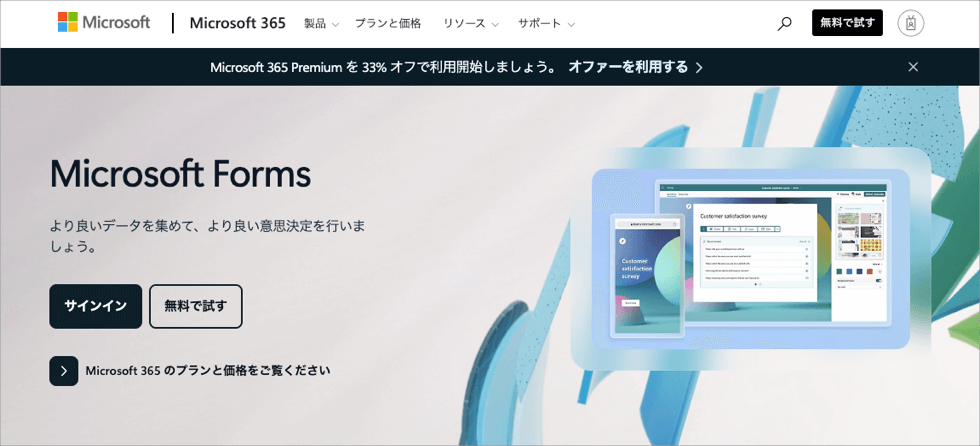
Microsoft Formsは、Microsoft 365(Excel・Teams・Outlook)と連携しやすいアンケートツールです。社内アカウントでの利用や、回答管理をExcelで行いたい場合に適しています。回答結果は自動でExcelに反映され、フィルターや関数を使った詳細な集計・分析にもすぐに活用できます。
Microsoft Forms を利用した作成方法を見るGoogleフォーム

Google フォームは、Googleアカウントがあればすぐに使える、手軽さが特徴のアンケートツールです。操作が直感的で、初めてアンケートを作る方でも迷わず進められます。回答結果はGoogleスプレッドシートに自動で集計され、リアルタイムでの確認や簡易的な分析もスムーズに行えます。
Googleフォーム を利用した作成方法を見る

